教育実習・保育実習
実習で実践力を身につける
講義や演習、そして実習へと段階を踏んだカリキュラム。
実習から事後の課題の取り組みまで、ハマタンの実習プログラムは確かな実践力を育てます。


-
講 義
保育者となるために必要な知識を学ぶ

-
演 習
子どもと楽しむ運動や音楽、工作や食育などを学ぶ

-
実 習
講義や演習で学んだことを保育現場で実践
実習には「教育実習」と「保育実習」の2種類があります
教育実習(Ⅰ・Ⅱ)
事前・事後指導+幼稚園実習
幼稚園教諭二種免許状取得のため
保育実習(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
事前・事後指導+保育所・社会福祉施設実習
保育士資格取得のため
年間スケジュール
1年次 後期[10月〜3月]
- 教育実習Ⅰ 2月
- 幼稚園[5日間]
- 保育実習Ⅰ 2月
- 保育所[12日間]
2年次 前期[4月〜9月]
- 教育実習Ⅱ 6月
- 幼稚園[15日間]
- 保育実習Ⅰ 7〜8月
- 社会福祉施設[12日間]
- 保育実習Ⅱ 9月
- 保育所[12日間]
- 保育実習Ⅲ 9月
- 社会福祉施設[12日間]
※保育実習ⅡまたはⅢのどちらかを選択して実習に行きます。
幼稚園の先生になるために
幼稚園での実習
幼稚園で実習を行う教育実習は、幼稚園の先生になるために必要な科目の一つです。実際に幼稚園で子どもたちと一緒に過ごし、実習先の先生方から指導を受けながら学びます。
幼稚園とは?
幼稚園は文部科学省管轄の学校です。満3歳から小学校へ入るまでの幼児が通うことができます。設置者が市町村など公立の園と、学校法人など私立の園があります。

STUDENT’S VOICE

実習を経験することで早く現場に出たいという
気持ちが大きくなりました
池田 羽那さん
(静岡県立浜松湖南高等学校出身)
実習先/学校法人長生学園 しらゆりこども園
実習では、子どもの前で手遊びや絵本の読み聞かせを行うことが多くあり、最初はとても緊張しました。しかし実際に経験することで、子どもの反応を見ながら行うことができるようになっていき、保育者も楽しんで行うことが大切だと学びました。初めての実習は何もかもが初めてで、時には憂鬱になってしまうこともありましたが、子どもたちと関わり笑顔を見ることができると、楽しさや喜びを感じ、早く現場に出たいという気持ちが大きくなりました。
保育士の資格を取得するために①
保育所での実習
保育士の資格を取得するために必要な実習の一つです。保育所について、講義や演習で学んできたことを実際に体験し、保育現場に立つことで保育士としての仕事について理解を深めます。
保育所とは?
保育所は厚生労働省管轄の児童福祉施設です。保護者が就労・妊娠・病気・介護などで子どもを保育することができないと認められる時、保護者の委託を受け、その乳児や幼児の保育を行います。

STUDENT’S VOICE

保育の仕事に携わることへの
責任や喜びを感じました
安富 凛さん
(浜松学院興誠高等学校出身)
実習先/社会福祉法人染葉会 豊田みなみ保育園
私は子どもたちへの言葉のかけ方や引きつけ方、保育者間での連携の大切さを学びました。座学では学ぶことのできない、実践的な活動を体験しました。責任実習では、子どもたちの様子や興味のあるものを捉え、計画しました。不安なことばかりでしたが、子どもたちの反応から達成感や新たな自分の課題を見つけられました。また、たくさん質問させていただき、専門的な知識をより深められたと思います。自分の保育者像を思い描くことができ、保育の仕事に携わることへの責任や喜びを感じました。
保育士の資格を取得するために②
施設での実習
保育士の資格を取得するために必要な保育所を除く社会福祉施設で行う実習です。社会的養護が必要な子どもたち、障害をもつ方々等の支援をする施設で福祉の仕事を体験し、学びます。
社会福祉施設とは?
大きくは、児童福祉施設と障害者支援施設に分けられます。児童福祉施設では、保護者と生活することができない環境にある子どものための施設として、乳児院や児童養護施設など、また、子どもたちに何らかの障害があり、家庭では生活できない子どものための障害児入所施設や、療育(発達促進)のための児童発達支援センターなどがあります。障害者支援施設では、入所している利用者の方々の日常生活の支援や就労に向けた訓練・支援などを行います。
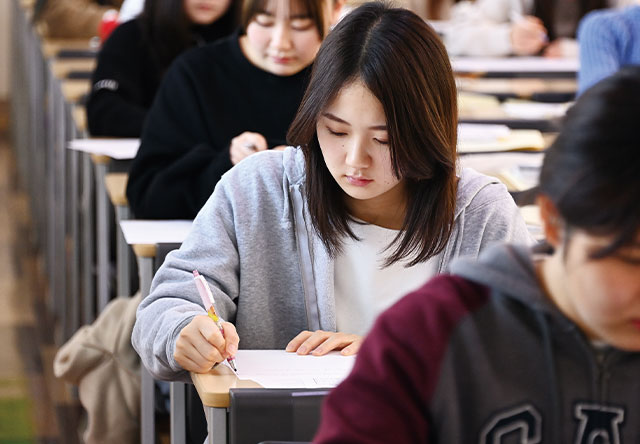
STUDENT’S VOICE

「褒める支援」が大切だと
教えていただきました
伊藤 里華さん
(静岡県立浜松商業高等学校出身)
実習先/富士市立ふじやま学園
実習を通して学んだことは障害についての知識や、利用している子ども一人ひとりの特徴について理解することが大切だということです。たくさんの子どもが利用していて、一人ひとり異なる背景があるため、障害の知識だけではなく子どもの性格なども理解し、その子に合った支援をすることが大切だと学びました。また「褒める支援」という支援の方法が大切だと教えていただきました。どんなに小さなことでも褒め、認めることで少しずつ自信につなげることができたり、信頼関係につながっていくことができたりすることを教えていただきました。
